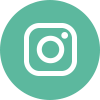宗像・沖ノ島と関連遺産群
<3> (新原・奴山古墳群)

▲1 「新原・奴山古墳群」の西側は、江戸時代に干拓されて農地となるまでは入海が広がっていた。古墳群の向こうには玄界灘が広がり、その海は中津宮のある大島、そして沖ノ島へと続く。沖ノ島に対する信仰を発展させた海に生きた人々による、海と結びついた信仰空間がうかがえる。
海に生きた人々の信仰空間を示す広大な墓域
玄界灘に沿って宗像地域を南北に貫く国道495号。車を走らせていると、福津市勝浦・奴山地区ののどかな田園風景のなかにいくつもの小さな山のようなものを確認できます。これこそが「新原・奴山古墳群」で、前方後円墳5基、円墳35基、方墳1基の計41基によって構成されています。
この古墳群は、宗像地域を支配した豪族、宗像氏が5世紀前半〜6世紀後半に、入海に臨む場所に築きました。福岡県世界遺産登録推進室の野木雄大さんは、「宗像氏は沖ノ島での祭祀を執り行っただけでなく、卓越した航海術を活かして、中国・朝鮮との交流を行っていました。さらに、現在の奈良県を中心としたヤマト王権と朝鮮半島にあった百済との交流を取り持ちました。そのため沖ノ島での祭祀では、ヤマト王権から数多くの奉献品が捧げられました」と、宗像氏が当時の国際交流にいかに貢献していたかを語ります。
一部、調査が行われた古墳からは、鉄製のかぶと、よろい、刀、剣のほか、のみ、きり、かんな、斧などの工具が発見されています。
古墳のある風景を後世に
「新原・奴山古墳群」を含む「宗像・沖ノ島と関連遺産群」は、聖なる島・沖ノ島に対する信仰が発展し、現代まで継承されてきた一連の過程を証明しています。「海を介した交流を背景とする古代祭祀のあり方が規模、内容ともに非常によく保存された、世界的にも稀な例です」とその価値を語る野木さん。「現在、専門家を招いての会議や一般の方を対象としたパネル展、公開講座などを行っています。まずはみなさんに、地元の資産に対する理解を深め、誇りを持っていただけると嬉しいです」と、世界遺産の登録に向けて期待を膨らませます。
-
宗像・沖ノ島と関連遺産群に関する問い合わせ先
住所:〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7
電話:092-643-3162
(福岡県世界遺産登録推進室)
【新原・奴山古墳群
(しんばる・ぬやまこふんぐん)】
住所:福岡県福津市勝浦、奴山

▲2 7号墳(5世紀前半)。入海に突き出た台地の先端部に位置する、宗像地域唯一の方墳。
沖ノ島の祭祀遺跡と共通する鉄斧などが出土しており、祭祀の場だったという説がある。

▲3 22号墳(5世紀前半)。全長80mの前方後円墳で、古墳群の中では最大。
周溝の周りには、幅10mほどの周堤が巡らされている。

▲4 30号墳(6世紀中頃)。全長54mの前方後円墳。
保存状態がよく、周辺から見ると形状がよく分かる。