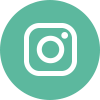英彦山神宮奉幣殿 ―添田町―

初日の出を福岡で最初に望むことができるのが大分県境にそびえる英彦山(1200M)である。霊験を感じるような奇岩が多く修験道 *1の本拠地として栄え、戦国期には僧坊が三千を超えると称された。中腹には石積みの塀や石畳の長い参道(写真▲1)が残り往時の繁栄ぶりがしのばれる。しかし、僧兵を有したことで戦国末期に戦火に巻き込まれ豊臣秀吉に征服されて勢力は弱小化した。
江戸初期に小倉藩を支配した細川忠興(ただおき)はこの地を庇護し1616年に奉幣殿を建立した。当初は講堂として造られ仏像も安置されていた。サワラ板の柿葺(こけらぶき)*2 入母屋(いりもや)造りの勾配が大きい反り屋根が印象的だ。朱塗りの柱や梁は太くて装飾は少なく廻縁(まわりえん)(写真▲2)の大床には手摺もない。平成14年の台風で裏山が崩れ大きな被害にあったが以前のように修復され、山中にありながら巨大でしかも修行の場にふさわしい豪壮な造りで入山者を迎えている。
参道の登り口には銅(かね)の鳥居があり、少し登ると財蔵坊(写真▲3)が往時の宿坊の様子を伝えている。宝篋印塔(ほうきょういんとう)と呼ばれる仏塔や雪舟様式の庭園跡、茶店などを覗きながら奉幣殿まで二時間余りかけて登ったが、のどがカラカラになってしまった。天之水分神(あめのみくまりのかみ)(写真▲4)の御神水の美味しかったこと。山伏の修行がいかに大変か悟った気分だった。
*1 修験道・・・古代からの山岳信仰に仏教が結びついた日本独特の混交宗教。山へ籠って厳しい修行をし、悟りを開くことを目指した。修行者は修験者または山伏と呼ばれる。
*2 柿葺・・・屋根葺手法の一つで、耐久性のある桧などの薄板を竹釘で重ね貼りする技法。板葺(いたぶき)の代名詞にも使われる。日本に古来伝わる伝統的手法で文化財の屋根で見ることができる。
-
場所・お問い合わせ
福岡県添田町英彦山 1アクセス
英彦山神宮奉幣殿
TEL:0947-85-0001JR日田彦山線「彦山駅」下車後、添田町営バス「英彦山」行バス「英彦山神宮下」下車。徒歩約20分。備考年中無休

▲1 長い参道

▲2 廻縁

▲3 財蔵坊

▲4 天之水分神