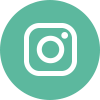岩屋神社本殿 境内熊野神社
―東峰村―

宝珠山の宝珠とはなんだろうと昔から疑問に思っていた。岩屋神社のご神体が宝珠であるという。それは本殿に安置され何重もの菰(こも)*1に包まれ、古来誰も見ることを許されていない。菰の取り換えは、氏子が目隠しをして手探りで行うという徹底ぶりだ。神秘のベールはその境内(けいだい)にも満ちていた。
神社の入口にあたる下宮(げくう)からきつい階段を上がると、うっそうとした木陰に無数の観音や地蔵の石仏が参内(さんだい)者を迎える。方向を転じ狭い洞門(どうもん)*2(▲1)をくぐり抜けてもやはり石仏群と階段があり、見上げると中宮(ちゅうぐう)の岩屋神社本殿の軒裏と明るい空がやっと視界に入る。たどりついてほっとする間もなく、のしかかった権現(ごんげん)岩に棟から先が飲み込まれた本殿の異形(いぎょう)(▲2)に驚かされる。危険な鎖場を垂直に降りて鎖をつたって馬の首根石(こうねいわ)(▲3)まで行くと眼下に棚田が見え、振り返ればそびえ立つ権現岩と本殿が再確認できる。上宮(じょうぐう)へ上ると、熊野神社(▲4)が高い崖の岩窟(がんくつ)に投げ入れられたようにへばりついている。特段の宗教心を持たない私でも天狗が造ったと信じたくなり霊験(れいげん)を感ぜずにはいられない。
古代548年に宝珠石が発見され彦山(ひこさん)とともに修験道の聖地となり、多くの行者が祠(ほこら)に立てこもり修行した。中世には境内に七堂伽藍(がらん)が立ち並び祭礼が盛んにおこなわれたと伝わっているが、戦国の争乱に巻き込まれ、ほとんどが焼かれてしまった。江戸時代1698年に藩主黒田綱政の助力により正面5間、奥行2間で杉皮と茅の重葺(かさねぶき)(▲5)の現在の本殿が建立された。熊野神社は1686年に完成した記録が残るが、一度も目立った修理をされず当初の形態を留めていて、非常に貴重な存在だ。日田彦山線の眼鏡橋や棚田(▲6)を訪れる人もぜひ足を伸ばしてもらいたい。これほど自然を巧みに利用した神域には早々お目にかかれない。
*1 菰・・・・わらを荒くあんで布状にしたもの(本文)
*2 洞門・・・洞穴の入口 ここではわざと岩に穴をあけ門の代りにしている。
-
場所
朝倉郡東峰村宝珠山字岩屋1414アクセスJR日田彦山線「筑前岩屋」駅より徒歩20分お問い合わせ東峰村役場 企画振興課見学
TEL:0946-74-2311年中開放

▲1 洞門

▲2 本殿

▲3 本殿

▲4 熊野神社

▲5 重葺

▲6 眼鏡橋や棚田