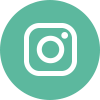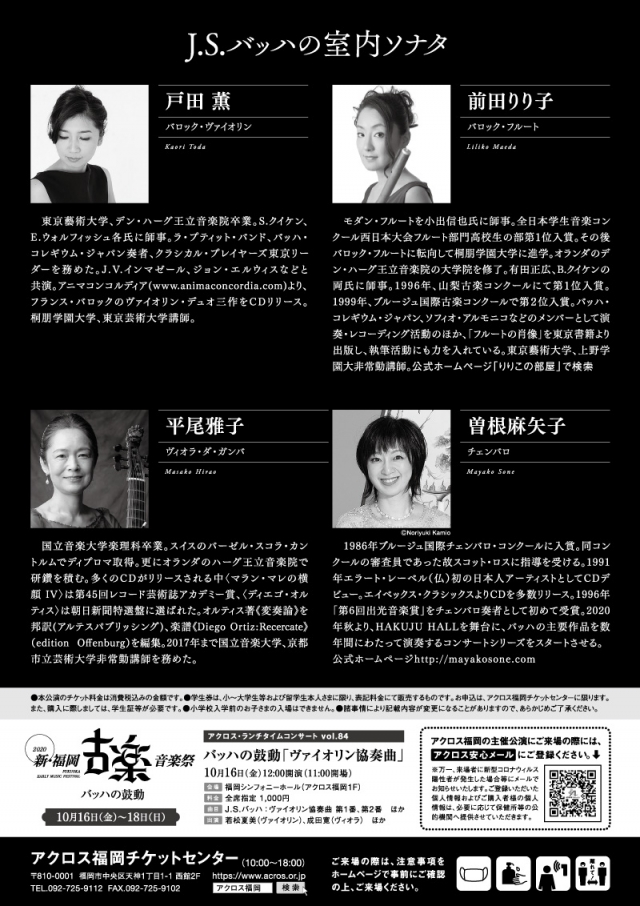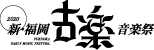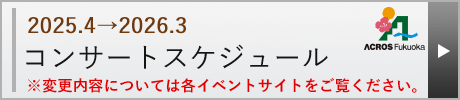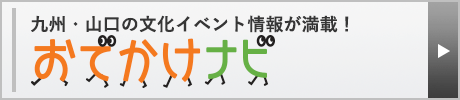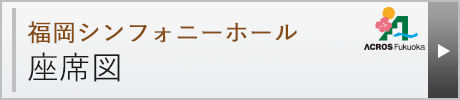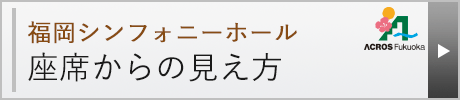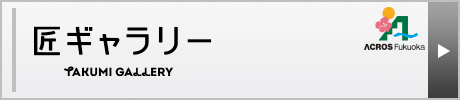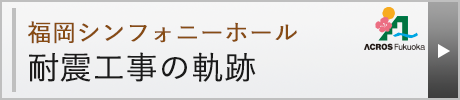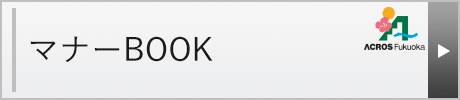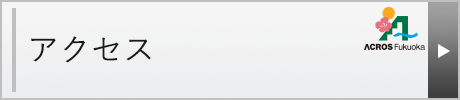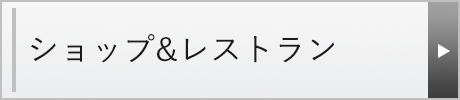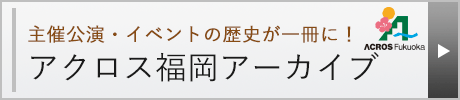J.S.バッハ(1685-1750)
フルートとヴァイオリンと通奏低音のためのトリオ・ソナタ ト長調 BWV1038 「トリオ・ソナタ」とは、バロック時代に広く愛好された室内楽のスタイルで、2つの旋律楽器と通奏低音による3声部で構成されるところからこの名がある。ただし通奏低音のパートはヴィオラ・ダ・ガンバなどの低音楽器とチェンバロ(和声的な肉付けを施す)が受け持つため、実際には4つの楽器で演奏される音楽である。バッハの時代はまさにそのトリオ・ソナタ全盛期であったが、意外にもバッハが残したトリオ・ソナタ作品は少なく、わずかに6曲を数えるに過ぎない(しかもその6曲の中には、バッハの真作とは認められないものも含まれている)。今回演奏されるト長調のトリオ・ソナタは、フルートとヴァイオリンを旋律楽器に用いた作品だが、偽作でJ.S.バッハがいた低音上に息子か弟子が旋律をつけたのではないかと思われる。教会ソナタのスタイルによる緩-急-緩-急の4楽章構成で、二つの旋律楽器の模倣書法を生かした第1、第3楽章に対して、急速な第2,第4楽章は通奏低音を加えた3声部書法によるフーガが展開する。 第1楽章ラルゴ、第2楽章ヴィヴァーチェ、第3楽章アダージョ、第4楽章プレスト。
フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV1034 バッハがフルートのために残した作品は、<無伴奏フルートのためのパルティータ>と<2つのフルートと通奏低音のためのソナタ>を含む8曲(フルートの8曲についても現在では1曲は完全に偽作といわれているので7曲)が知られている。バッハの時代には横笛のフルート・トラヴェルソと縦笛のブロックフレーテの2種類が使われていたが、いずれの曲も、フルート・トラヴェルソのために作曲されたものである。<フルートと通奏低音のためのソナタ>は3曲を数えるが、今回演奏されるホ短調の一曲は、まことにバッハらしい名作として知られる。教会ソナタの4楽章構成(緩-急-緩-急)をとり、第1楽章の哀愁漂う旋律の息づかいや第3楽章の気品に満ちた表情などに、フルートの表現力が引き出される一方、第2楽章で繰り広げられる2声のフーガや、第4楽章の活気あふれる舞曲風の小気味よいリズムに軽やかな魅力が発揮される。 第1楽章アダージョ・マ・ノン・タント、第2楽章アレグロ、第3楽章アンダンテ、第4楽章アレグロ。
オブリガートチェンバロ付きヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ 第3番 ト短調 BWV1029 ヴィオラ・ダ・ガンバはバロック時代に活躍した楽器で、イタリア語で「脚のヴィオラ」を意味するその名前は、楽器を脚で支えることからつけられた。バッハはケーテン宮廷楽長時代に、3曲のヴィオラ・ダ・ガンバのためのソナタを作曲しているが、それは宮廷楽団にC.F.アーベルという優れたガンバ奏者がいたためと考えられている。おそらくバッハ自身がチェンバロを受け持って、これらの曲は演奏されたのだろう。このト短調の一曲は一般的な教会ソナタの4楽章構成ではなく、急―緩―急の3楽章構成で書かれており、協奏曲のスタイルを念頭に作曲されたと推察される。<ブランデンブルグ協奏曲第3番>の冒頭楽章を想わせる第1楽章は、主題素材のモティーフ労作によって組み立てられ、活気あふれる第3楽章も<ブランデンブルグ協奏曲第5番>の終楽章を想わせる。一方第2楽章は、ガンバとチェンバロの右手が連綿と旋律を歌い交わす気品あふれる音楽となっている。 第1楽章ヴィヴァーチェ、第2楽章アダージョ、第3楽章アレグロ。
オブリガートチェンバロ付きヴァイオリン・ソナタ 第6番 ト長調 BWV1019 バロック時代のヴァイオリン・ソナタは、いわゆる「通奏低音付きソナタ」の形で書かれるのが普通で、この場合、伴奏を受け持つチェンバロには低音(左手)と和声を示す数字が与えられるだけで、チェンバロ奏者は即興的に伴奏をつけるのが慣習だった。しかしバッハは、そのチェンバロ・パートの右手に綿密な書き込みを行い、後世のいわゆる「二重奏ソナタ」の先駆となる作品を作り上げた。こうした<オブリガートチェンバロ付きヴァイオリン・ソナタ>をバッハ全部で6曲残している。
今回演奏されるト長調の一曲は、第3楽章にチェンバロ独奏の楽章を置いた全5楽章で構成され、快速なイタリアの協奏曲風楽章で始まる。緩やかな第2楽章と第4楽章はいずれも深い情感と悲哀感をたたえる。そして終楽章は対位法書法による快活な曲想で結ぶ。 第1楽章アレグロ、第2楽章ラルゴ、第3楽章アレグロ、第4楽章アダージョ、第5楽章アレグロ。
「音楽の捧げ物」BWV1079より トリオ・ソナタ
バッハ晩年の2つの労作<フーガの技法>と<音楽の捧げ物>は、対位法芸術の粋を集めた金字塔として名高い。<音楽の捧げ物>は、1747年にバッハがポツダムの宮廷を訪れた際、即興演奏のテーマとしてフリードリヒ大王から与えられた主題をもとに、後日一連の対位法的楽曲として作曲し大王に献上したもので、2曲のリチェルカーレと10曲の各種カノン、そして今回演奏されるトリオ・ソナタから成る。2曲のリチェルカーレとともに曲集中もっとも充実した内容を誇るこのトリオ・ソナタは、全4楽章の教会ソナタのスタイルによる、豊かな旋律性と緻密な構成美に裏付けられた名作。フルートとヴァイオリンが旋律楽器に用いられているが、フルートはフリードリヒ大王が愛好していた楽器であった。 第1楽章ラルゴ、第2楽章アレグロ、第3楽章アンダンテ、第4楽章アレグロ。
曲目解説:柿沼 唯(作曲家)
|